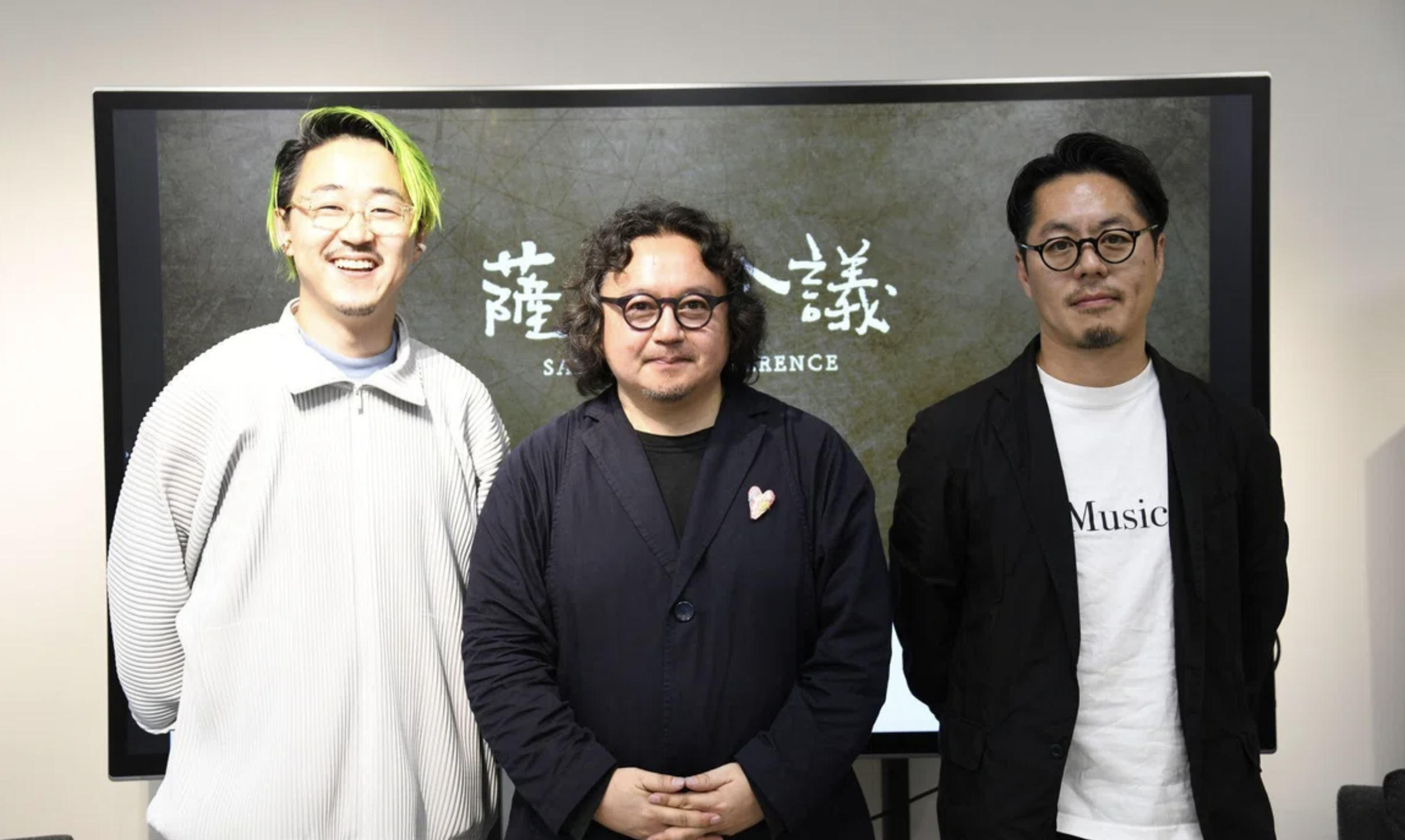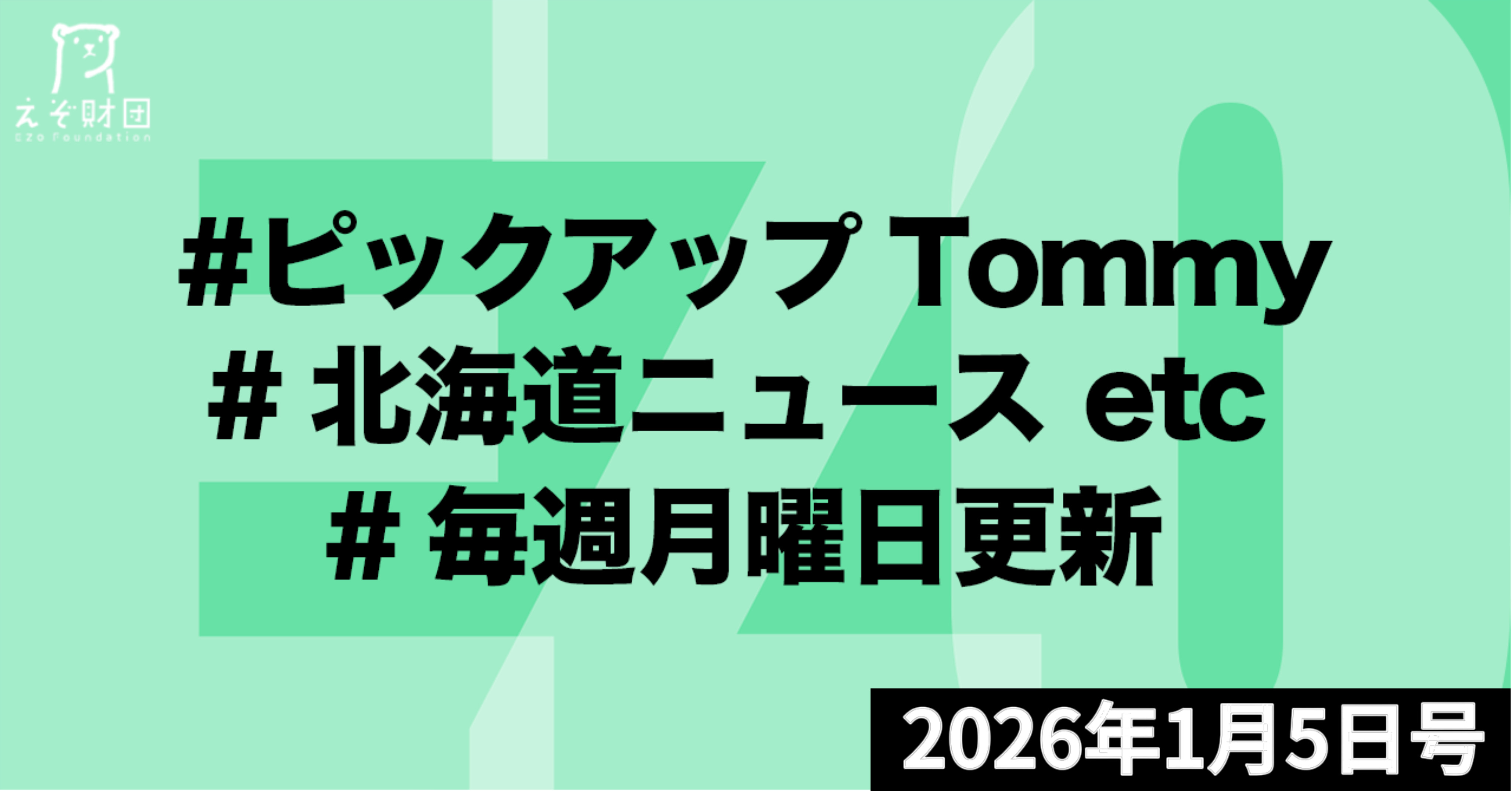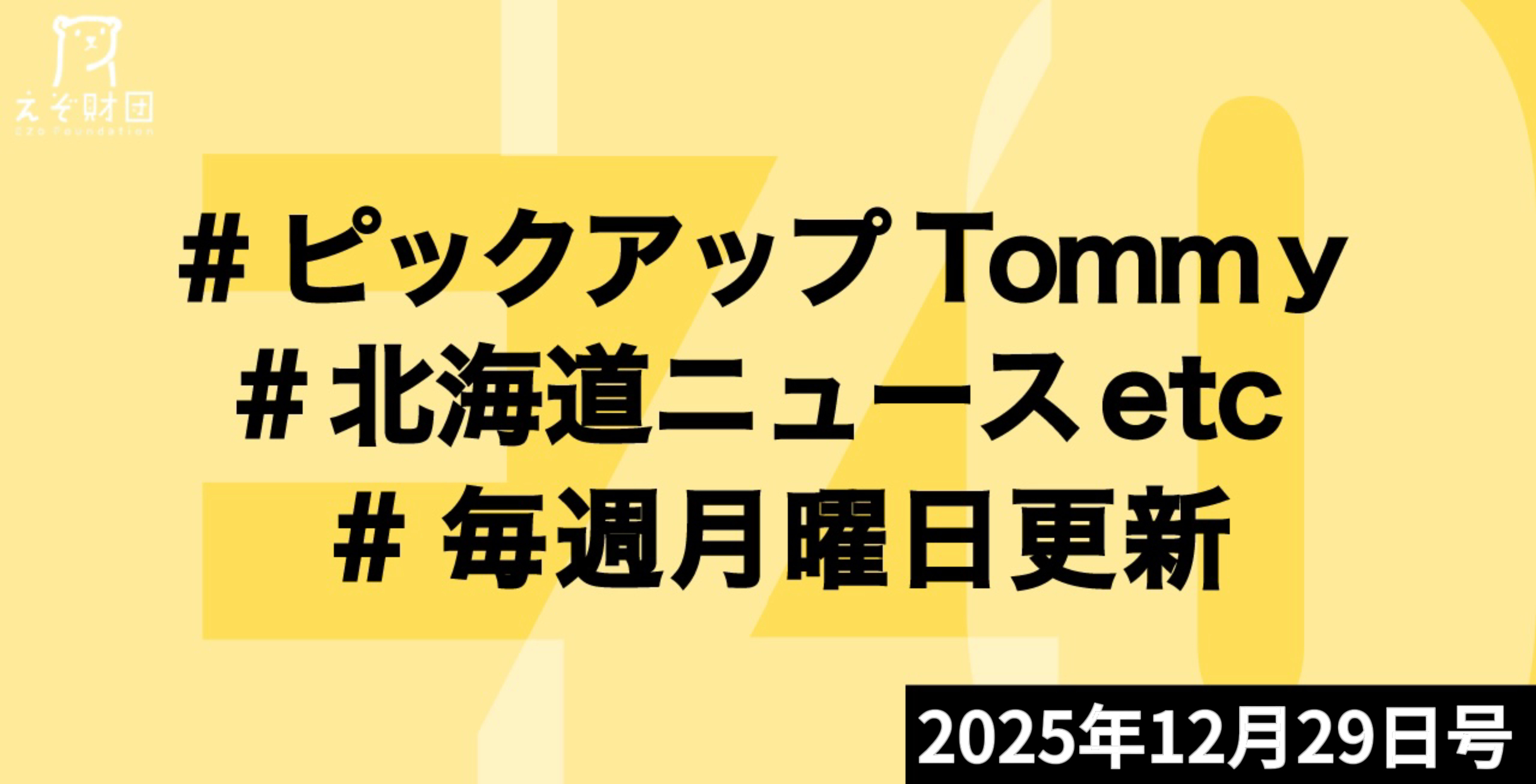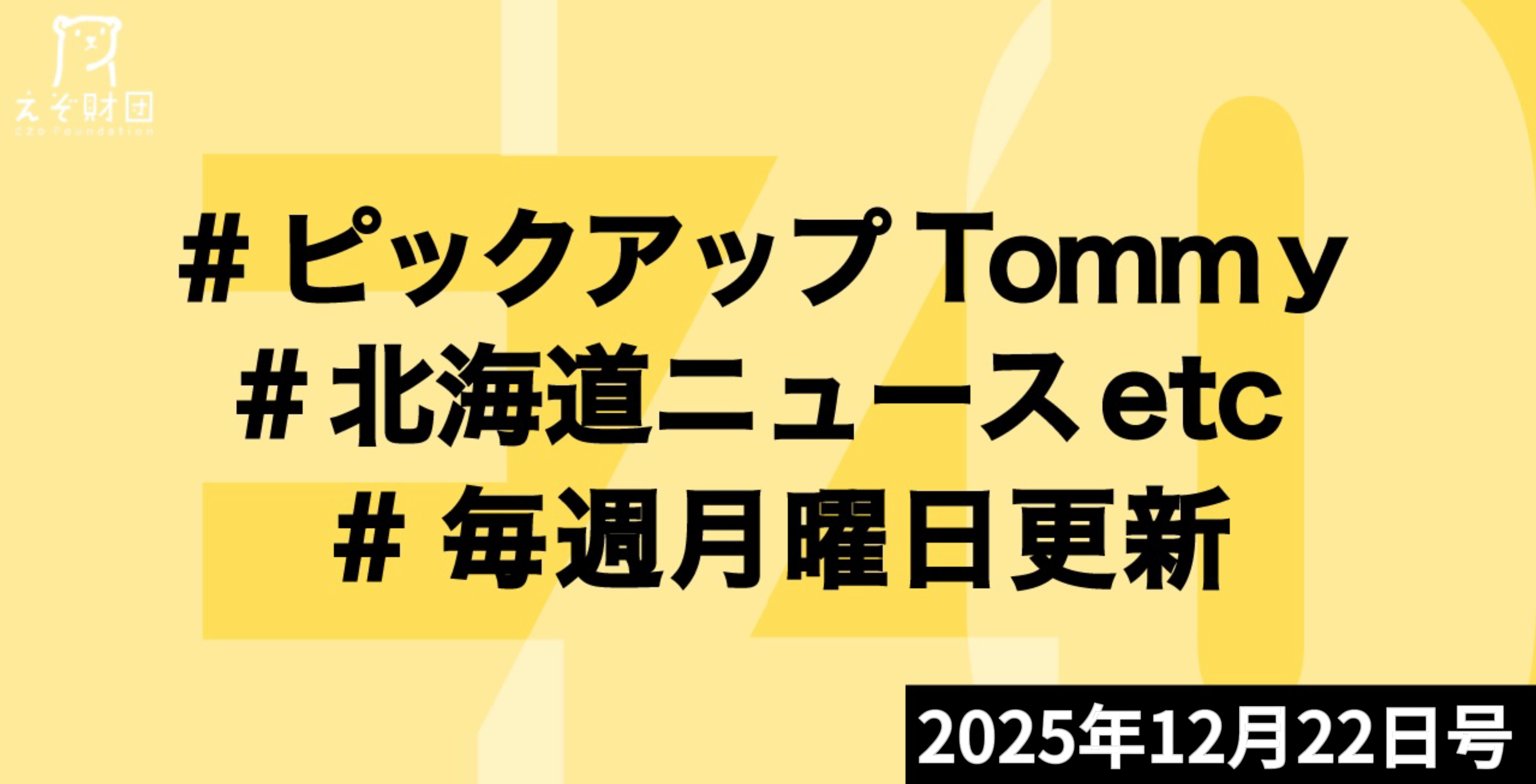- TOP
- 【#えぞ財団】連載企画「#この人、エーゾ」⑭離島経済新聞社/ツギノバ(利尻町)・大久保さん ~利尻町を選んだ理由と今後の展望とは?自分自身の存在意義~

【#えぞ財団】連載企画「#この人、エーゾ」⑭離島経済新聞社/ツギノバ(利尻町)・大久保さん ~利尻町を選んだ理由と今後の展望とは?自分自身の存在意義~
えぞ財団
2022年4月1日
組織のなかで、マチのなかで、もがきながらも新たなチャレンジをしているひとを紹介する「この人、エーゾ」。今回ご紹介するのは、大久保昌宏さん。東京都出身で、2010年離島経済新聞社を設立。現在、利尻町に拠点を移し、一般社団法人ツギノバを設立。町と連携しながら、利尻町定住移住支援センターツギノバの運営や定住移住、企業誘致、起業・創業・継業支援などに取り組んでいます。
目次
- 東京出身の元広告制作会社マンが利尻島に!仲間と立ち上げた”離島経済新聞社”
- リトケイとは?きっかけは仲間と行った離島で触れた”島の豊かさ”
- 離島への想いをビジネスに。繰り返された苦労、議論。6852の島からなる”島国・日本”
- 現在は利尻町を拠点に活動、そのきっかけは?
- プロジェクトを通し築いた信頼、さらに利尻町へ出向。町のマスタープラン策定支援へ
- 利尻町や離島への熱い思いがぶつかる事もあったパートナー利尻町役場佐藤さんの存在
- 想い出の校舎を残したい!廃校を”マチのハブ”に!動き出したプロジェクト
- 地域を支える利尻町定住移住支援センターの役割
- 数ある選択肢の中で利尻町を選んだ理由と今後の展望とは?自分自身の存在意義
大久保昌宏(おおくぼ・まさひろ):1979年東京都生まれ。特定非営利活動法人離島経済新聞社理事・一般社団法人ツギノバ代表理事。広告制作会社等を経て、 2010年、株式会社離島経済新聞社設立し、2014年、特定非営利活動法人化に伴い事務局長就任、2021年より現職。さらに現在、利尻町に拠点を移し、一般社団法人ツギノバを設立。町と連携しながら、利尻町定住移住支援センターツギノバの運営などに取り組む。趣味は飲み会と読書。
東京出身の元広告制作会社マンが利尻島に!仲間と立ち上げた”離島経済新聞社”
日本最北端の稚内市からフェリーで約1時間半にある利尻島の利尻町に大久保さんは現在、拠点を置き”特定非営利活動法人離島経済新聞社理事”と”一般社団法人ツギノバ代表理事”の2つの肩書で忙しくも充実した日々を送っています。東京都出身の大久保さんは2010年、全国の有人離島を対象にしたメディアを運営する株式会社離島経済新聞社を仲間と立ち上げました。きっかけは、その年から通い始めた”スクーリング・パッド”という専門スクール。東京都世田谷区の廃校となった中学校校舎を利活用した複合型施設”IID 世田谷ものづくり学校”で開催していたそのスクールは、起業や独立、スキルアップなどを目指す受講者に、各業種の現場で活躍するプロが経験や知見に基づいた学びや気づきを教えてくれるカリキュラムを提供していました。「当時、広告制作会社に勤めていた僕は、今後のキャリアを模索しているタイミングでした。10代の頃に手に取った雑誌に憧れ、編集者になったものの、媒体のコンセプトも含めて根幹に携われる人はごくわずか。であれば、自分でメディアを立ち上げればいいと考え、最終的に起業することを前提に様々な媒体を渡り歩き、広告の仕組み・営業・制作を経験できる当時の職場は想定していた最後の修行の場だった」と当時を振り返ります。大久保さんが次のステップをどう踏み出そうか迷っている時に、同じタイミングで入学した仲間たちと出会い、2010年10月に株式会社離島経済新聞社の設立に至りました。
リトケイとは?きっかけは仲間と行った離島で触れた”島の豊かさ”
離島経済新聞社(略称:リトケイ)は、全国の有人離島を対象にした情報発信を行う会社として、有人離島専門ウェブメディア「ritokei」、有人離島専門フリーペーパー「季刊ritokei」といったメディアの運営・発行を手掛けると同時にさまざまな離島地域の地域づくりや人材育成等を行っています。株式会社として設立され、2014年からNPO法人離島経済新聞社となり、大久保さんは2015年度〜2020年度まで代表理事を担いました。
「離島経済新聞社というと、大体の人は意味不明な顔をして『なんで離島なんですか?』と聞いてくる。確かに意味不明なんです(笑)。設立メンバーに島とゆかりのある人は1人もおらず、むしろデザインや編集という、いわゆるクリエイティブ系の仕事を生業として、島とは正反対の都市部で生きてきた面々。そんな僕らが離島地域にフォーカスしたのは、たまたまみんなで広島県のある島に行ったことがきっかけでした。2010年当時はFacebookが日本で流行り始め、twitterの利用者が徐々に増えていた頃。全国的にどの地域も情報発信においては今ほど洗練されておらず、これまで名前も聞いたことがなかった島のことをインターネットで調べてみても、その島の魅力がほとんどわかりませんでした。ところが現地に着いてみると、すれ違う子どもたちが僕らを見て大きな声で挨拶し、地元の魚を売り歩く行商のおばちゃんたちが島のことを丁寧に教えてくれる。農家のおじちゃんは『この島は宝島だ』と言い、僕らはその言葉にとても共感し、納得しました。島の人たちと時間を共有し、なんとなく「豊かさ」を感じました。当時はその豊かさの正体がわからりませんでしたが、今思えば『コミュニティとしての豊かさ』なのだと思います。物質的なものではないけれど、そこにいる人たちの存在、営みの積み重ねによって成立するもの。当時の僕らはその一端に触れ、こういう地域としての魅力をもっとたくさんの人に知ってもらいたいと考えたんです」と話してくれました。
離島への想いをビジネスに。繰り返された苦労、議論。6852の島からなる”島国・日本”
離島について調べると、日本は6852の島からできていてそのうちの約420もの島に人が住んでいます。「420ほどの島にある素晴らしい魅力を発信できないだろうか?人口が少ない小さな島であっても、一つのプラットフォームを作れれば、情報過多の社会においてもたくさんの人の目に留まるのではないか?日本の外周を取り巻く離島地域の多種多様な魅力が発信できれば、日本という国そのものの魅力を高めることができるのではないだろうか?そんなことを毎晩遅くまで議論し、生まれたのがリトケイなんです」結局、島に縁もゆかりもなかった大久保さん達は、実際に島に行き、そこで暮らす人たちに触れたことで、いつの間にか島のことを勝手に自分ごととして捉え、走り出しました。
「設立当初は島の情報発信をしたいというだけで、ビジネスモデルを全く考えておらずとても苦労しましたが、いろんな島の方々から応援してもらい徐々に認知度を高めることはできました。」それに伴い、運営メディアに対して都市部の企業から広告の問い合わせなどもいただくようになった大久保さん達。「ある日、全国にチェーン展開する大手スーパーマーケットから出店を目的とした広告出稿依頼があり、一瞬みんなで喜んだものの、よくよく考えてこれを引き受けたら実際にスーパーが出店し、島の商店を営む人は廃業することになるんじゃないか?という疑問が浮かびました。」これまで携わってくださった島の方々の顔が脳裏をよぎり、様々な議論を重ねた結果その依頼は断る事にしたそうです。「今だったら企業も島も巻き込み、みんなで話をしていくような別のやり方を提案していたかもしれません。」設立してしばらくはこのようなことが続き、その度に自分たちのスタンスを考え、組織としてのビジョンやミッションなどについて議論を繰り返したと大久保さんは話します。
現在は利尻町を拠点に活動、そのきっかけは?
利尻町とのつながりは、リトケイの活動として2014年から本格的に始まりました。きっかけは公益財団法人日本財団とリトケイとの共同事業「うみやまかわ新聞」事業。新聞づくりを通じて「地域への愛着」を醸成し、テレビ電話による「他地域との交流」を体験できる小学校高学年向けの教育プログラムです。リトケイスタッフが講師となり、地域の社会教育事業や小学校の年間カリキュラムの一つとして実施していました。組織変更したばかりの当時、この取り組みがNPO法人としての最初の事業。「日本財団からの助成金と自分たちの自己資金での運営となるため、まずは事業趣旨を理解し、受け入れてくれる地域が必要でした。リトケイの取り組みの中で知り合った様々な地域の人たちにお声がけをして、つながったところの一つが利尻町。初めて利尻島を訪問したのは2014年7月。目の前に広がる風景が他の離島地域とは異なる雄大さ、美しさで驚いたことを今でも鮮明に覚えています。島に着いたその日の晩、町の飲食店に集まってくれた利尻町役場の方々は、僕らのプレゼンを真剣に聞いてくれて、その場で取り組みへの協力を快諾してくれました。同時に、事業実施のために地域内の民間プレーヤーを地域コーディネーターとして起用したいという、半ば無茶振りのような僕らの考えにも付き合ってくれて、一緒に口説き落とすのを手伝ってくれたりもした。とてもフランクでフットワークも軽く、積極的に協力してもらえたことが印象に残っています。」と語ります。日本財団とリトケイとの共同事業という形でのうみやまかわ新聞の取り組み実施は2019年度で終了したが、利尻町は教育委員会の事業として終了後も継続していて、今も利尻町から委託を受けてリトケイが関わっているそうです。
うみやまかわ新聞 | 利尻島|りしぷら RISHIRI PLUSうみやまかわ新聞 | りしぷら RISHIRI PLUS
https://www.rishiri-plus.jp/umiyamakawashinbun/
プロジェクトを通し築いた信頼、さらに利尻町へ出向。町のマスタープラン策定支援へ
その後、2016年に国土交通省の事業のコーディネーターとして利尻町を担当したり、その事業がきっかけで2017年にNORTH FLAGGERSという漁師団体の立ち上げに関わった大久保さんたち。「町との関わり方も自主事業に協力してもらう立場から、仕事を依頼され一緒に事業に取り組む立場へと変わっていきました。大きな転機になったのは、2018年に総務省の地域おこし企業人制度を活用して、離島経済新聞社から利尻町へ出向になったこと。主な業務内容は町のマスタープランとなる第六次総合振興計画の策定支援。元々は、利尻町役場から計画策定を外部事業者に委託したいのだが、予算も限られており何かいい方法はないだろうかという相談をいただいたことから地域おこし企業人制度を紹介し、外部事業者に出向で来てもらうのはどうだろうか、という提案をさせてもらいました。当然、委託を想定している外部事業者へ話をするものだと思っていましたが、返ってきた答えは『離島経済新聞社は来られる?』」リトケイもNPO法人で理事会もあり、一緒に動いている職員もいるので、本来であればみんなに相談しなければいけないところだが大久保さんは即答で言ってしまった。「もちろんです」と。
利尻町や離島への熱い思いがぶつかる事もあったパートナー利尻町役場佐藤さんの存在
この話が出る半年ほど前、大久保さんは明け方の東京の居酒屋で派手な怒鳴り合いをしたそうです。2017年度の国土交通省事業のコーディネーターとして利尻町を2年連続で担当させてもらい、その事業の有終の美を飾る最後のイベントの日。「無事に終わったイベントの打ち上げで、当時の利尻町担当者としてご一緒していた佐藤弘人さん(当時:係長)と二次会、三次会と流れていく中で、最終的に残ったのは僕らとほぼ寝落ちしてしまっているリトケイスタッフの3人。明け方4時近くに佐藤さんは僕に利尻町の課題や、その課題解決のためにやりたいことを熱く語ってくれました。『町の未来地図をみんなで描きたい。一つ実現していく度にみんなで喜んで、最終的に全てを実現した時にみんなで胴上げしたい。』僕は『いいですね!いつやるんですか?』と聞きました。佐藤さんの答えは『うーん、いつだろうな…』僕自身も酔っ払っていたので記憶が定かではないのですが、その曖昧な答えになぜかカチンときてしまって。お互いが段々とヒートアップして、怒鳴り合いになっていました。その日は最終的に「いつか一緒にそれをやりましょう」と仲直りをして終わったのですが、僕はうみやまかわ新聞をスタートした時に積極的に受け入れてくれた利尻町の方々の姿を見ていたし、利尻町以外の島の方々で様々なことに取り組んでいる姿も見てきていたので、アルコールの勢いもあって、やりたいことがあるのに何でやらないんだ!とカチンときてしまって。」その後、総合振興計画の担当となった佐藤さんから前述の話があった時は「嬉しかったですね。町のマスタープランこそ、大きな未来地図じゃないか、と。総合振興計画の策定支援を通じて、100人近い町の人たちの話を聞いていく中で、課題・理想・現実などいろんな話が出てきましたが、地域の良いところ、好きなところの話もたくさんありました。地域としての魅力を持続しさらに高めていくために総合振興計画があるのなら、これまでの地域としての積み重ねを否定するようなものにはしたくないし、これまでの積み重ねの上に「もっとこうしたい」という思いをさらに重ねて、地域の特色・魅力を伸ばしていけるようなものにしたいと思いましたね。」
【えぞ財団】連載企画「この人、エーゾ」① 利尻町役場まちづくり政策課・佐藤さん~ぶっ飛んだ地元PRも「未来への投資」、固定概念は「ぶっ壊したい!」~
想い出の校舎を残したい!廃校を”マチのハブ”に!動き出したプロジェクト
総合振興計画策定を進めていた過程で、閉校になった旧沓形中学校校舎の利活用について町から相談を受けた大久保さん。「閉校になった後、取り壊すには莫大な予算が必要となるとのことでした。実際に校舎内を見せてもらうと、まだ学校として使っていた頃の面影がそこかしこに残っていて、椅子や机にも当時の生徒の名前が書かれており、その名前のほとんどが、うみやまかわ新聞に参加していた子どもたちの名前でした。」高校までしかない利尻島では、ほとんどの生徒が18歳で島を一度出ることになる。「ここに名前がある子どもたちが18歳になり、島を出て、年末年始や成人式、夏休みで戻ってきた時にこの校舎がなくなって更地になっていたらどう感じるだろうか。僕ら自身もリトケイを立ち上げる時に世田谷区の廃校施設「IID 世田谷ものづくり学校」を利用していて、卒業生たちが訪れ思い出話をしたり、地域内外の人たちがオフィスやイベント等で訪れつながりが生まれたり、地域の中に自分の居場所ができたり、という姿を実際に見てきたこともあり、町の中でさまざまなハブになれるような場所にしたらどうだろうかという提案をさせていただきました」結果として校舎は無償貸与をしてもらい、町との協働で利尻町定住移住支援センター「ツギノバ」が設立され、少しづつ校舎を改修整備しながら現在も利活用を進めています。
地域を支える利尻町定住移住支援センターの役割
利尻町定住移住支援センター「ツギノバ」については、総合振興計画を策定中、町の人口減少・少子高齢化を不安視する声をたくさん聞いた中で、地域の魅力を持続・向上していくためには、そもそも地域が持続しなければいけない。そのためには人口減少・少子高齢化に歯止めをかけていく必要がある、という議論の中から生まれた機能だそうです。「利尻町は、現在年間約30人〜50人が毎年町から転出しています。地域存続のためには、まずこの人数を減らしていく必要がありますが、安易に移住者を増やそうというのは順序が違うと僕は思っています。町から出ていく30〜50人が何故出ていくのか対応できていないのに、新たに町外からの移住者を求めようとするのは都合が良すぎると。まずは出ていく人たちを減らすことに注力して、その結果、この町に暮らし続けたいと思う人が増えれば、町外からの移住者も自然に増えると考えているんです。まず町の人たちが定住する、その結果としてその先の移住推進が成立する。利尻町定住移住支援センターはそのための場所であり、すでに町に住んでいる人からの暮らしを続けていくための相談と、移住希望者からの相談窓口を設けています。」地域内外の人たちが気軽に訪れられるように、カフェラウンジやコワーキングスペース、多目的スタジオなども設けて、いろんな人が交わり、つながれるコミュニティスペースとしての機能も有している利尻町定住移住支援センター。現在は、小中学生向けの塾や町民の方々のイベントの受け入れなども行なっているそうです。4月からは、新たに地域外の企業を誘致するためのサテライトオフィススペースもオープン。すでに2社の入居が確定しており、今後町の中で新たな雇用が生まれたり、新しい取り組みが始まることが期待できます。
数ある選択肢の中で利尻町を選んだ理由と今後の展望とは?自分自身の存在意義
大久保さんは、2020年度でリトケイの代表理事を退任し、利尻町で一般社団法人ツギノバを立ち上げ、現在は利尻町定住移住支援センター内にオフィスを設けています。「そもそもリトケイは東京に本社を有する組織で、まもなく丸8年を迎える利尻町との関わりの中で、この地域に根を張って取り組んでいきたいと考えた時によそ者としてではなく地域の一員になるためにはどうしたらいいかと。その答えの一つが利尻町内で新たに法人を設立することでした。リトケイでつながりのある方々からは、利尻町でツギノバを立ち上げたことについて「なぜ利尻町?」と聞かれます。理由はいくつもありますが、主な理由の一つはコミュニティとしての豊かさですね。リトケイ設立前に出会った広島県の島で得た共感や感動、豊かさ。そういったものが2014年に初めて訪れた利尻町でも感じられ、それは関わる時間が増えるほど確信に変わり、豊かさという言葉に対する僕自身の解像度が高まっていっている気がしました。結果としてこの豊かさが持続するためにはどうしたらいいのか、この地域にできるだけ長くいたい、と考えるようになったんですね。」リトケイの仕事を通じて全国たくさんの島に行っている大久保さん。「どの島がオススメですか」との質問にはこう答えるそう。「これも前述の「なぜ利尻町」問題と同じで、最終的に行き着くところは「人」だと思います。人そのものの魅力というよりは、その地域で暮らす人が形成するコミュニティに触れた時に息苦しいと感じるのか、楽しいと感じるのか。シンプルに言えば、僕は利尻町で楽しいと感じたから、ここにいたい。それに尽きると思うんですよね。」それに付随して、働き方・生き方。リトケイでは立ち上げ段階からリモートワークが当たり前で、オンライン会議等も2010年段階からかなり頻繁に取り入れていたそうです。「働く場所は快適に仕事ができればどこでもいい。僕自身は現在、利尻町の他に鹿児島県や東京都の島でも仕事をしていますが、現地に行くのは月に1回の出張くらいです。であれば、自分が楽しく快適に健やかに暮らしていける地域で生活したい。ひょんなことから地域づくりの仕事に携わらせていただき、僕自身もこの地域に関わらせてもらうことで成長させていただいたし、地域、まち、島などに対する考え方も深めることができました。これからも利尻町にいるプレーヤーの1人として、自分が居続けたい、暮らし続けたい地域を考えていきたいと思うし、そのための取り組みを進めていきたい。そしてどこかのタイミングで、佐藤さんが言っていた「胴上げ」をみんなでできればいいと思います」
Video
記事コンテンツ
Membership
地方の経営者による、
地方の経営者のための学び
「松山ローカル大学」はメンバーを募集しています
Price
会員料金
受講生
会員ならではの特典を活用して しっかり学びたい方におすすめ
月額11,000円(税込)
- 会員限定の交流イベントの参加
- 全講座の参加権利(優先案内あり)
- 講座アーカイブ視聴
※懇親会のみ実費
企業パートナー
従業員への教育ツール、情報のキャッチアップにおすすめ
年額660,000※円(税込)
(※請求書一括払い)
月額55,000円(税込)
- ロゴ掲載
- 会員限定の交流イベントの参加
- 全講座の参加権利(2名参加可能)
- 講座アーカイブ視聴(社内利用可)
※懇親会のみ実費
Partner’s Contents
日本各地のパートナーが発信する情報
Video
動画コンテンツ
Article
記事コンテンツ
Category
カテゴリ













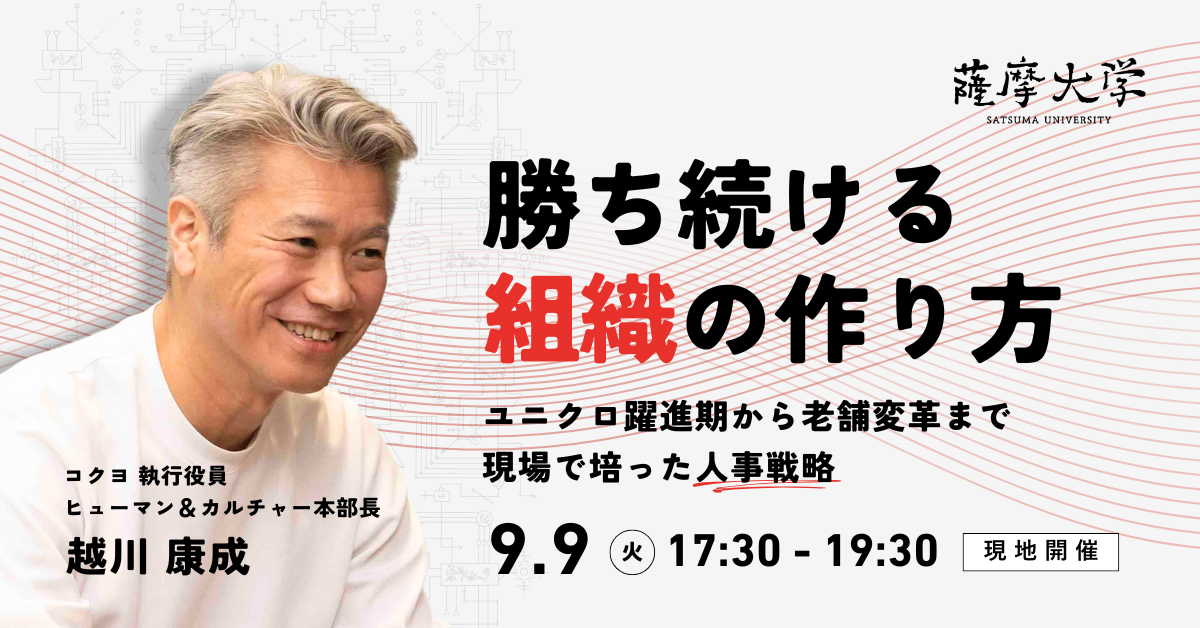

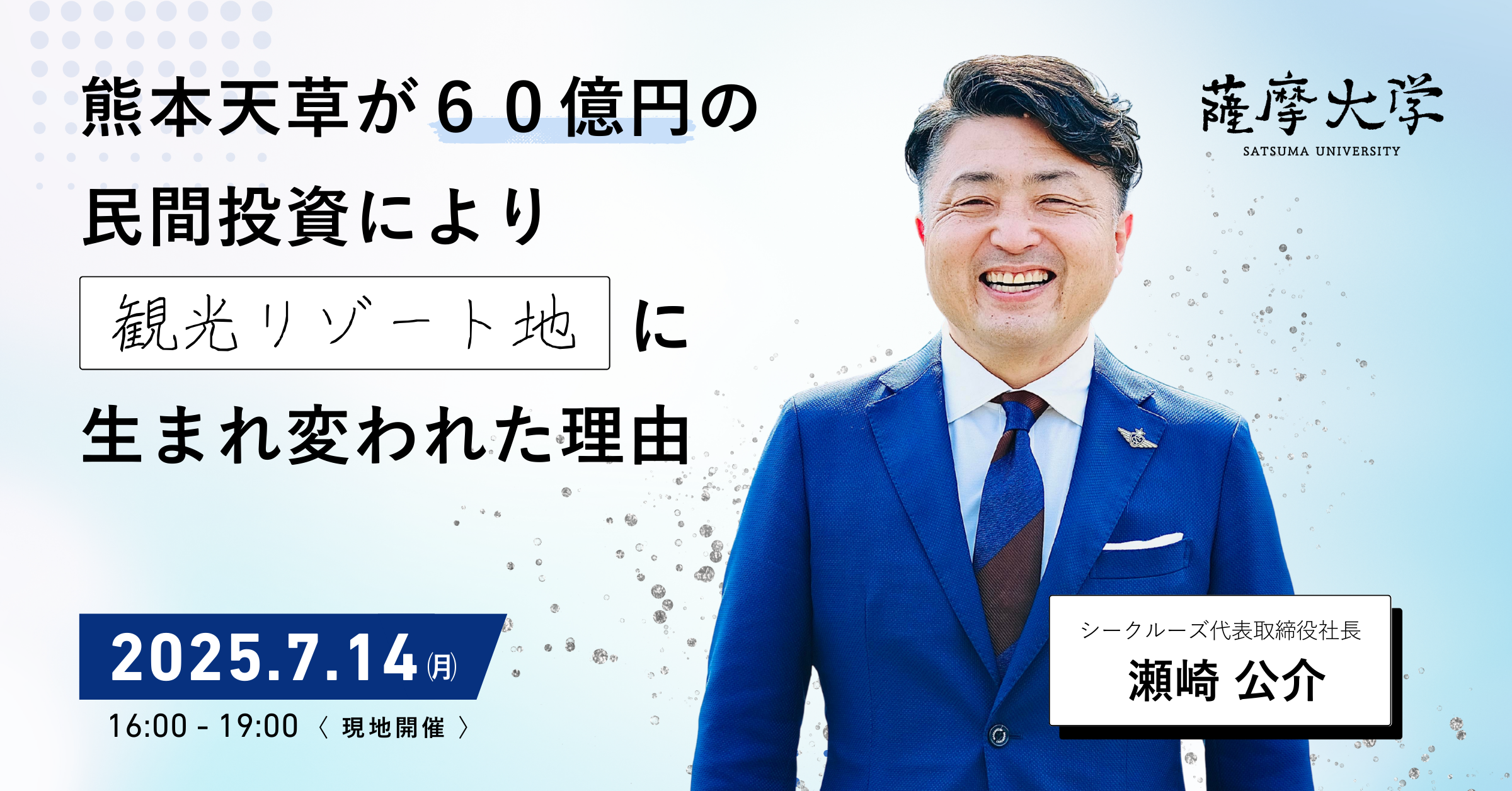



.png)